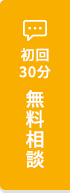覚醒剤輸入罪の知情性についての義務的推定を示したと思われる事例
最高裁平成25年10月21日刑集67巻7号755頁
【判示事項】
密輸組織が関与する覚せい剤の密輸入事件について,被告人の故意を認めず無罪とした第1審判決に事実誤認があるとした原判決に,刑訴法382条の解釈適用の誤りはないとされた事例
第1 公訴事実の要旨は次のとおりである。
本件公訴事実の要旨は,「被告人は,氏名不詳者らと共謀の上,営利の目的で,平成22年6月2日(現地時間),ベナン共和国所在のカルディナル・ベルナディン・ガンティン国際空港において,航空機に搭乗する際,粘着テープ等で2包に小分けされた覚醒剤2481.9g(以下「本件覚醒剤」という。)を隠し入れたスーツケース(茶色のソフトスーツケースであり,以下「本件スーツケース」という。)を機内預託手荷物として預けて同航空機に積み込ませ,同月3日(現地時間),フランス共和国所在のシャルル・ド・ゴール国際空港において,本件スーツケースを別の航空機に積み替えさせて出発させ,同月4日,成田国際空港内において,本件スーツケースを同航空機から搬出させ,もって覚醒剤取締法違反である覚醒剤の輸入を行うとともに,同日,同空港内の税関の旅具検査場において,税関職員の検査を受けた際,前記覚醒剤を携帯している事実を申告しないまま同検査場を通過して輸入しようとしたが,同職員に覚醒剤を発見されたため,遂げられなかった。」というものである。
第2 判旨
1 所論は,事実誤認を理由に第1審判決を破棄して自判した原判決は,事実誤認につき論理則,経験則等に照らして不合理であることを具体的に示しておらず,刑訴法382条の解釈適用を誤った違法があり,ひいては事実誤認があるという。
2 原判決は,知情性を否定した第1審判決の結論について,次のとおり説示して,判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるという。すなわち,覚醒剤密輸組織によるこの種の犯罪において,運搬者が,覚醒剤密輸組織の者からにしろ,一般人を装った者からにしろ,誰からも何らの委託も受けていないとか,受託物の回収方法について何らの指示も依頼も受けていないということは,現実にはあり得ないというべきである。
この経験則と被告人が大量の覚醒剤が隠匿された本件スーツケースを携帯して来日したことなどからは,被告人は本件スーツケースを日本に運ぶよう指示又は依頼を受けて来日したと認定でき,渡航費用等の経費は覚醒剤密輸組織が負担したと考えられることなども併せ考えれば,被告人において,少なくとも,本件スーツケースの中に覚醒剤等の違法薬物が隠匿されているかもしれないことを認識していたと推認できる。
3 1,2審判決が前提とするとおり,本件覚醒剤の量や隠匿態様等に照らし,本件密輸には覚醒剤密輸組織が関与していると認められるところ,原判決が説示するとおり,密輸組織が多額の費用を掛け,摘発される危険を冒してまで密輸を敢行するのは,それによって多額の利益が得られるからに他ならず,同組織は,上記利益を実際に取得するべく,目的地到着後に運搬者から覚醒剤を確実に回収することができるような措置を講じるなどして密輸を敢行するものである。
そして,同組織にとってみれば,引き受け手を見付けられる限り,報酬の支払を条件にするなどしながら,運搬者に対して,荷物を引き渡すべき相手や場所等を伝えたり,入国後に特定の連絡先に連絡するよう指示したりするなど,荷物の回収方法について必要な指示等をした上,覚醒剤が入った荷物の運搬を委託するという方法が,回収の確実性が高く,かつ,準備や回収の手間も少ないという点で採用しやすい密輸方法であることは明らかである。
これに対し,そのような荷物の運搬委託を伴わない密輸方法は,目的地に確実に到着する運搬者となる人物を見付け出した上,同人の知らない間に覚醒剤をその手荷物の中に忍ばせたりする一方,目的地到着後に密かに,あるいは,同人の意思に反してでもそれを回収しなければならないなどという点で,準備や実行の手間が多く,確実性も低い密輸方法といえる。
そうすると,密輸組織としては,荷物の中身が覚醒剤であることまで打ち明けるかどうかはともかく,運搬者に対し,荷物の回収方法について必要な指示等をした上で覚醒剤が入った荷物の運搬を委託するという密輸方法を採用するのが通常であるといえ,(これに反して通常とはいえないことから裁判所の経験則を適用できないのは)荷物の運搬の委託自体をせず,運搬者の知らない間に覚醒剤をその手荷物の中に忍ばせるなどして運搬させるとか,覚醒剤が入った荷物の運搬の委託はするものの,その回収方法について何らの指示等もしないというのは,密輸組織において目的地到着後に運搬者から覚醒剤を確実に回収することができるような特別な事情があるか,あるいは確実に回収することができる措置を別途講じているといった事情がある場合に限られるといえる。
したがって,この種事案については,上記のような特段の事情がない限り,運搬者は,密輸組織の関係者等から,回収方法について必要な指示等を受けた上,覚醒剤が入った荷物の運搬の委託を受けていたものと認定するのが相当である。
4 これを本件についてみると,被告人の来日前の渡航先であるケニア共和国及びベナン共和国については,これらの国が密輸組織の目指していた本件覚醒剤の密輸の目的地であり,同国内で密輸組織が本件覚醒剤を確実に回収できるようになっていたなどの事情はうかがわれない。
5 所論は,ベナン共和国で被告人のガイド兼運転手をする予定であったBが密輸組織の回収役であった可能性があるというが,第1審判決も指摘するとおり,本件覚醒剤は,実際には日本に運ばれている上,被告人が供述するBの行動等は,ベナン共和国への飛行機の到着時刻が予定よりも3時間ほど遅れたところ,到着時には空港におらず,その後も同国滞在中に電話を3,4回かけてきたにとどまるというのであって,密輸組織の回収役の行動として不自然といわざるを得ず,回収役とみる余地はない。
日本における確実な回収措置等の有無について見ても,被告人に同行者がいなかったことや,日本到着時に宿泊先のホテルの予約がされておらず,被告人自身,日本において誰かと会う約束もなく,日本における旅程も決めていなかったと述べていることなどに照らすと,密輸組織がそのような被告人から本件覚醒剤の回収を図ることは容易なことではなく,日本到着後に被告人から本件覚醒剤を確実に回収できるような特別な事情があるとか,確実に回収することができる措置が別途講じられていたとはいえない。そうすると,本件では,(通常のケースとして裁判所の経験則を適用しないという)上記の特段の事情はなく,被告人は,密輸組織の関係者等から,回収方法について必要な指示等を受けた上,本件スーツケースを日本に運搬することの委託を受けていたものと認定するのが相当である。
原判決が,この種事案に適用されるべき経験則等について「この種の犯罪において,運搬者が,誰からも何らの委託も受けていないとか,受託物の回収方法について何らの指示も依頼も受けていないということは,現実にはあり得ない」などと説示している点は,例外を認める余地がないという趣旨であるとすれば,経験則等の理解として適切なものとはいえないが,密輸組織が関与した犯行であることや,被告人が本件スーツケースを携帯して来日したことなどから,被告人は本件スーツケースを日本に運ぶよう指示又は依頼を受けて来日したと認定した原判断は,上記したところに照らし正当である。
原判決は,そのほか,被告人の来日目的は本件スーツケースを日本に持ち込むことにあり,また,被告人の渡航費用等の経費は密輸組織において負担したものと考えられるとし,さらに,そのような費用を掛け,かつ,発覚の危険を冒してまで秘密裏に日本に持ち込もうとする物で,本件スーツケースに隠匿し得る物として想定されるのは,覚醒剤等の違法薬物であるから,被告人において,少なくとも,本件スーツケースの中に覚醒剤等の違法薬物が隠匿されているかもしれないことを認識していたと推認できるとし,このような推認を妨げる事情もないとしているが,この推認過程や認定内容は合理的で,誤りは認められない。
6 以上に対し,第1審判決は,「(密輸組織による回収のための措置としては)様々なものが考えられ,運搬者に事情を知らせないまま同人から回収する方法がないとまではいえない」という前提の下,「被告人が本件覚醒剤が隠匿された本件スーツケースを自己の手荷物として持ち込んだという事実から,特別の事情がなければ通常中身を知っているとまで推認することはできない」と説示し,最終的に被告人の知情性は認定できないという結論を導いている。
この点は,この種事案に適用されるべき経験則等の内容を誤認したか,あるいは,抽象的な可能性のみを理由として経験則等に基づく合理的な推認を否定した点において経験則等の適用を誤ったものといえ,原判決のとおり,知情性を否定した結論が誤っているといわざるを得ない。
7 以上によれば,原判決は,第1審判決の事実認定が経験則等に照らして不合理であることを具体的に示して事実誤認があると判断したものといえ(最高裁平成23年(あ)第757号同24年2月13日第一小法廷判決・刑集66巻4号482頁参照),刑訴法382条の解釈適用の誤りはないし,事実誤認もない。
なお,原判決が,第1審判決について,事実認定の方法自体において誤っているとした説示には,所論指摘のとおり第1審判決に対する誤った理解を前提とする部分も含まれているから,そのまま是認することはできないが,この点は結論に影響しない。
第3 解説
1 「回収措置に関する経験則」
(1) 密売組織の関与
まず、「回収措置に関する経験則」を適用するには、覚醒剤の密売組織の関与が必要となる。もっともこの点も非常に認定は粗雑であり、①覚醒剤の量が多いこと、②隠匿態様が巧妙であるか否か―の2点を問題にして、①覚醒剤の量が個人の輸入としては多く、②隠匿態様が手の込んだものであれば「密売組織の関与」なるものが認定されることになる。
本件では、①覚醒剤の量は2.5キロであり多いと評価することができるし、②スーツケースについては側面に細工が施されており、ほぼ問題なく「密売組織の関与」が認定できる。
(2) 回収措置に関する経験則
ア 原則
刑事裁判では、証明責任を負うのは検察官であるが、覚醒剤輸入罪では経験則の利用により証明責任が転換されているといえる。
そして、密売組織としては、運搬委託をして指定場所まで運搬してもらい、荷物の回収についての指示をする方法によるのが効率的であるので、通常、運搬委託を受けていないというのはあり得ないというのである。
イ 例外
(ア)荷物の運搬の委託自体がないことが明白な場合
(イ)運搬者(被告人)の知らない間に覚醒剤をその手荷物の中に忍ばせたことが明白である場合
(ウ)回収方法に指示がなく被告人からどのように覚醒剤を回収するか確実な事情があることが明白であること場合
(エ)密売組織が確実に回収することができるような特別な事情があるか否か
ウ 解説
密売組織が関与していると決め打ちしたうえで、組織は利益を実際に取得するため、より確実性の高い密輸方法を選択して密輸を行うという机上の空論を設定している。
そのうえで、確実性の高い密輸方法とは、通常は運搬者に対して回収方法につき必要な指示等をしたうえで薬物が隠匿された荷物の運搬を委託する方法を採用するのが通常であるから、特段の事情がない限り、当該荷物の回収方法まで必要な指示を受けたうえでその運搬の委託を受けたものと認定できるとしたのである。いわば一種の決め打ちである。
そうだとすれば特段の事情があることに注目が集まることにな
るが本来は検察官が特段の事情がないことの立証をすることが必
要であると解すべきではないか。
なお、注意を要するのは最高裁調査官の匿名コメントでも、「中身が薬物であることまで打ち明けられているか否か」は重要な事実ではないと指摘されている。したがって、この点の主張を繰り返しても事実認定上は仕方ないと思われる。
特段の事情についてみると、①密輸組織において目的地到着後に運搬者である被告人から覚醒剤をある意味では意思によらずして確実に回収することができるような特別な事情があるか否か、②密輸組織により意思によらずして確実に回収することができるような措置を別途講じているような事情があるか否かである。
しかしながら、この経験則は相当に問題が多く、経験則自体があいまいで抽象的とのそしりは免れないだろう。調査官解説に準ずるコメントすら、「具体的にどのような場合を指しているのかは必ずしも明らかでないが、前段の理由付けに照らすと、荷物の運搬委託がなかったとしても密輸組織において薬物を運搬者から確実に回収できたといえるような特別な事情があること、運搬委託とは別の回収業者に依頼しておくといった何らかの別働の回収のための措置・手当てが密輸組織によって別途講じられている可能性がある場合をいう。匿名コメントは例外の範囲について「広く含ませる趣旨」としている。
典型例として調査官解説が挙げるのは次のような事例である。
すなわち、①運搬者である被告人の交際相手が密売組織であった疑いが濃厚な場合について、交際相手が犯罪者であったことから運搬の委託はなかったものの、交際相手が荷物の回収が可能な状況にあったといえる場合が考えられるかもしれない。加えて②運搬者である被告人は身体が不自由であることから日本到着後は密輸組織の掌中にあるものの場合は、ある意味では別働の回収のための措置・手当てが密輸組織によって別途講じられている可能性がある場合といえる。
2 「運搬委託+費用負担=認識の経験則」
この点も、驚いた話であるが、特段の事情がない限り運搬委託があると看做されるので費用負担もしていた場合は認識していたとなるという事例判断の理解になっているようである。この点、これだけで認識の経験則になることも驚きであるが、密売組織側が費用負担をしており社会通念上不合理な程度、例えば30万円など負担している場合は知情しているとみなされても仕方ない面もあるから、「費用負担してもらっている事実」というのは、重要な事実といえる。
3 携行輸入型と密輸型
携行輸入にも該当することであるが、こと密輸型については、①覚醒剤の生産状況、②日本国内の需要状況、③関与する密売組織の活動状況、④摘発状況―について経験則も変化するのであって、経験則は証拠によって明らかにすべきときが多いと解される。
4 「傘をさしている人がいたら雨が降っている」のか
アメリカでは合理的な疑いの基準は、アメリカの刑事手続きの機構のなかで必須の役割を演じている。それは事実誤認に基づく有罪認定の危険を減少させるための第一の道具とすべきが無罪の推定である。これは定理ともいうべき初歩的な原則であり、憲法や刑事訴訟法の基礎であるというのである。
これに対して、無罪の推定どころか、「有罪の推定」をしていることになり、被告人のあずかり知らない可能性がある密輸組織の行動について被告人側に主張・立証責任を負わせることになり、適正手続を保障した憲法31条に違反すると考えるべきであろう。そのような理論的視座から、保守的な経験則の適用でなければならない。なお、本件では、「渡航費用の経費負担」についての事実認定はないが東京高裁が推論に推論を重ねて「そのような被告人が自ら渡航費用等の経費を負担したとは考え難く」とあるように、私見が上述のとおり重要な事実関係であり、費用負担していないことの検察官の証明がなさない限り利益原則に従うべきものと考えるが、これでは空中楼閣よりもろいものとすらいえよう。
これでは、立法機関ではない裁判所が覚醒剤密輸罪の法律を書き換え、事実上、覚醒剤の認識の推定規定を創設しているに他ならないことになるのであって、罪刑法定主義からいっても憲法31条に違反するといわざるを得ない。
5 アメリカでは、「ルール・メイキング」は許されないとの流れにあるといわれている。マラニー対ウィルバーでは、原審裁判官が本件のような経験則の推定をするとの説明を陪審員にしたところ、連邦最高裁はデュー・プロセス条項に違反するとされた。そのうえで連邦最高裁は、被告人が、「突然の挑発による激情に基づくものであるとの証拠の優越を示さない限り、謀殺と推認される」というのである。
この点、連邦最高裁は、検察官が突然の挑発による激情が存在しないことを合理的な疑いを超える程度に証明しない限り、謀殺罪で有罪とされるべきではないとの判断を示している。
推定には、許容的推定と呼ばれ刑事弁護の中で推定の受け入れを拒否でき不意打ちにならないものはデュー・プロセスに違反しないが、ほとんどが義務的推定となり、この場合、反証を許さない限りはデュー・プロセス条項に違反しているとするようである。
ゆえに、本件では特段の事情という反証の余地は残るが、実際反証の余地はほとんどなく、憲法31条に適正手続(無罪推定の原則)、罪刑法定主義(ルール・メイキングをしている)に違反するだろう。
本件では、覚醒剤を巧妙に大量に持っていると、密輸組織関与事件と義務的推定され、荷物の運搬委託契約があると推認される。なお、第三者の費用負担がない限り、違法薬物の認識の推定は反証されるとの見解があるようである。この見解を本件で採用したかについては、そのように読める説示箇所があるうえ、「考えられる」旨の判示など推論であることを前提にしており、第三者による費用負担は、反証可能性を広める可能性はわずかであるがあるといえよう。
そもそも罪刑法定主義という故意ないし共謀の観点からも問題があり、実体法上の解釈としても、また、無罪推定ないし利益原則が憲法上の原則と解する私見からすれば、少なくとも被告人側の拒否を許す、許容的推定程度の参考として参照されるのは格別、この事例判例によりルールメイキングがなされたと解することは憲法31条に違反しており到底許容することができないというべきであろう。こうした評価が分かれる判例を出したところで、第一審裁判所がついてくるのかも疑問とさえいえよう。
現実に原田國男「事実誤認の意義」は、「ここで注意しておくべきことは、論理則、経験則違反説でも心証の形成を前提としていることである。心証を形成しないで有罪・無罪の判断はできない。論理則、経験則違反だけでは、有罪、無罪の結論を得ることはできない」と指摘されている。これは、心証形成は従来の手法を用いて、破棄の際は、合理的理由が必要となるから、事実上、理由不備、理由齟齬を誤魔化す理論ということを原田自体が自白しているとすらいうほかないと思われる。つまり、「回収措置に対する経験則」は裁判員裁判を破棄する上訴審において、その合理性を具体的に示す説得の論理といえるところはあるが、それが行為規範足り得るのか、単なる民法的な裁判規範に過ぎないとすれば、極めて疑問であるが、高裁判事経験者たちの評釈をみると概ね最高裁に好意的であり、高裁執務の在り方を示しているとはいえるが、一審ではやはり許容的推定程度に考えておくべきものと思われる。この他に、知情性とは別に問題となる共謀の否定などの争い方もあり得よう。
匿名コメントも平成24年判例の要請を満たす控訴審判決の一例を示したということで、刑事訴訟法382条の事実誤認の意義について「第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることをいう」と判示している(最高裁平成24年2月13日)。この不合理であることを具体的に示すことが控訴審の判事たちからすると難しいという話しの限りにおいて有意ととらえるべきかもしれない。
しかし、これでは、控訴審や上告審で被告人に犠牲になってもらいながら「思考実験」をしたにすぎないだけというのは皮肉が過ぎるであろうか。
【審級】
東京高等裁判所平成24年4月4日平成23年(う)第1158号
千葉地方裁判所平成23年6月17日平成22年(わ)第1190号
【評釈】
季刊刑事弁護81号133頁
研修792号21頁
ジュリ1466号196頁
ジュリ1496号81頁
捜査研究63巻4号2頁
法曹時報67巻10号263頁