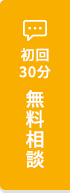不作為の殺人かー糖尿病患者の家族にインスリン投与を止めさせた者の罪責
未必的な不保護をもって、不保護の故意のある者と共謀の上、声明維持に必要な措置(糖尿病Ⅰ型のインスリンの投与)をさせず死亡させた者の殺人罪の成否
~最高裁令和2年8月24日平成30(あ)第728号 殺人被告事件
立命館大学法務博士、弁護士 服部勇人
第1 事案の概要
1 公訴事実
Xは、当時7歳の男児Vの母親YからVが離婚しているⅠ型糖尿病
について相談を受けて両親の間で治療を引き受けることを約束した。
そして、Xは両親に対してインスリンの投与の中止すればVが死亡することを認識しつつ、両親に対してインスリンの投与を中止させた。Xの指示は、Yがインスリンの投与なしに糖尿病の治療ができるとYが信じていることに乗じたものであった。
Xは、平成27年4月5日ないし27日、両親に対し、メールないし口頭でVに対するインスリンの投与の中止するよう指示し、両親をして、4月6日の投与を最後にインスリンの投与をせずに放置をさせた。
この次第でVは、4月27日午前6時33分、Ⅰ型糖尿病による衰弱で死亡した。
2 擬律について
検察官は、主位的に、被告人が両親を道具として本件犯行に及んだ旨の間接正犯を主張した。そして予備的には、被告人が両親と共謀して本件犯行に及んだ旨の共謀共同正犯の主張をしていた。一審は、母親との関係では主位的請求(間接正犯)を認定し、父岡との関係では予備的請求(共謀共同正犯、ただし保護責任者遺棄致死の限度)を認定した。東京高裁平成30年4月26日判決も控訴を棄却した。
3 上告理由
朝日新聞の報道では、インスリンを打たないと決めたのは両親であり殺意がないとの上告理由であったという。なお、控訴趣意では、①母親とお間で殺人の間接正犯を認めたこと、②Xの殺意を認めたことに事実誤認があると主張していたものである。上告棄却。
第2 判旨
「被告人は,生命維持のためにインスリンの投与が必要な1型糖尿病に罹患している幼年の被害者の治療をその両親から依頼され,インスリンを投与しなければ被害者が死亡する現実的な危険性があることを認識しながら,医学的根拠もないのに,自身を信頼して指示に従っている母親に対し,インスリンは毒であり,被告人の指導に従わなければ被害者は助からないなどとして,被害者にインスリンを投与しないよう脅しめいた文言を交えた執ようかつ強度の働きかけを行い,父親に対しても,母親を介して被害者へのインスリンの不投与を指示し,両親をして,被害者へのインスリンの投与をさせず,その結果,被害者が死亡するに至ったものである。母親は,被害者が難治性疾患の1型糖尿病にり患したことに強い精神的衝撃を受けていたところ,被告人による上記のような働きかけを受け,被害者を何とか完治させたいとの必死な思いとあいまって,被害者の生命を救い,1型糖尿病を完治させるためには,インスリンの不投与等の被告人の指導に従う以外にないと一途に考えるなどして,本件当時,被害者へのインスリンの投与という期待された作為に出ることができない精神状態に陥っていたものであり,被告人もこれを認識していたと認められる。また,被告人は,被告人の治療法に半信半疑の状態ながらこれに従っていた父親との間で,母親を介し,被害者へのインスリンの不投与について相互に意思を通じていたものと認められる。
以上のような本件の事実関係に照らすと,被告人は,未必的な殺意をもって,母親を道具として利用するとともに,不保護の故意のある父親と共謀の上,被害者の生命維持に必要なインスリンを投与せず,被害者を死亡させたものと認められ,被告人には殺人罪が成立する」。懲役14年6か月。
第3 解説
1 本件では、殺人の実行行為、即ち殺人の結果発生惹起に向けた現実的可能性ある行為が認められるか。本件では、XはYに対してメールないし口頭でVに対するインスリンの投与の中止を指示していたといえるから、間接正犯に該当するかが問題となる。Xに殺人罪を帰責する方法として不作為の殺人罪に犠律する方法、間接正犯には両親を道具として犠律する方法、共謀共同正犯(60条)として帰責する方法である。
2 結論から言えば、主位的訴因を間接正犯として、予備的訴因を共謀共同正犯としたのは、理論上前者の方が重く後者の方が軽いからである。仮に、間接正犯の訴因で共謀共同正犯を認定する場合は、縮小認定することになる。
ゆえに、刑事実務では、検討の順が間接正犯、共謀共同正犯という検討の順番になっている。なお、本件では、不作為の殺人とするより、両親との共同正犯として犠律しようとの試みであるが、両親はいずれも不起訴になっており、不作為犯の事実認定の不都合を避けるために共謀共同正犯の理論を持ち出しているとの指摘もあり得よう。
3 本件では、「不作為の殺人罪」が成立しないかという問題との混同がみられる。「不作為の殺人罪」を肯定したいわゆるシャクティ・パット事件(最決平成17年7月4日刑集59巻6号403頁)との対比の故である。シャクティ・パット事件は、病院から運び出させた上、必要な医療措置を受けさせないまま放置して死亡させたというものであり未必的殺意に基づく殺人罪を認め、殺意のない親族との間では保護責任者遺棄致死罪の限度で共同正犯になるとされている。
シャクティ・パット事件では、ホテルに運び込んだ後の放置が犯罪事実とされたことから不作為による殺人罪とされている。これに対し本件では、糖尿病治療の故というものもあるが治療場所は自宅であり、Xはインスリンの不投与という不作為を指示している。しかしながら、インスリンの不投与自体は不作為であるがXの行為自体が不作為であるかは議論が分かれる。
4 私見は、Xは治療の依頼を受けた者であるから保証人的立場にあり、積極的に殺害することも、重度の糖尿病でインスリンを奪うという不作為によってもいずれも容易に人を殺すことができるので、「作為と不作為の構成要件的同価値性」が認められるというしかなく不作為犯が成立すると解する余地もある。そのうえで、Xに間接正犯が成立しないかを検討するというのも実務上の考え方としては良いのではないだろうか。本件では、①結果発生の危険に重大な原因を与えたといえるし、②インスリンはXのYに対する指示自体であり危険性はコントロールされている、③インスリンは個人でも注射でき結果発生の防止も容易であるし、④XはVの治療を引き受けたものであるから、Xには作為義務が存するかという観点からみてこれを肯定することができる。
ただし、道具性がある間接正犯が認められる場合は、不作為犯の構成要件該当性判断において、作為義務という実質的な判断を行い罪刑法定主義に反する可能性もあるから、まず間接正犯の検討を行うことが憲法31条からみても、量刑上からみても相当性があるといえる。
これに対して、Xの行為は不作為犯ではなく作為犯であるという見解もある。この点に関し、Xの行為を作為か不作為がを論じることにはほとんど意味がないと思われる。なぜなら、間接正犯でもほとんど作為を伴わないものも少なくなく、構成要件に触れる行為をしているとは限らないことは当然の前提とされるからである。
ただし、本件は作為犯というように実質的利益衡量をして、罪刑法定主義違反、量刑の重い方から検討していくという点から妥当性があることに照らして、作為犯と強調する見解もあり得るだろう。
特に、原審の匿名コメントによれば、被告人の所為自体は不作為ではないとされ、指示の内容は不作為であるが被告人の所為は作為であり、母親との関係では間接正犯とされている。なお前田雅英教授も本件は被害者の両親に命じインスリンを投与させないことにより殺害した作為犯とされているものの、前田教授は間接正犯が不作為犯的なとらえ方をしているためトートロジー的なものに陥っているように思われる。いずれにしても局所的にXの行為を詳細に認定すれば、Vにインスリンを投与しないように脅しめいた行為をYに執拗な働きかけを行っていたなどの事実を認定判断すれば、保護者的立場にある両親がインスリンを投与しないという行為を作為で実現したと位置付けることはできるというべきである。
なお、松宮説は「救助的因果経過の阻止」としてこの場合は作為犯になることを当然の前提としている。「救助的因果経過の阻止(又は遮断」は明示的な定義は不明であったが、「病人と看護契約を結んだのに看護をせず患者を死なせた看護人は患者の死亡の原因となるような作為をしていない。そこで作為をしようとする自己の意思決定過程に干渉して不作為を決め込もうとする動きに、結果との間の因果関係を肯定する見解がある。松宮説がいう救助的因果経過の阻止は、物理的因果性の有無を問わないとしており、意思の抑圧も因果性の根拠となり得るとしており、「ピンディングの干渉説」に近いものをいうのではないかと考えられる。加えて、松宮説は、不真正不作為犯を罪刑法定主義違反としつつ、いわゆる不真正作為犯は「偽装された作為犯」として多くのものを取り込むため、松宮説ではもともと多くのものが作為犯になるということに留意しておく必要があるのであろう。ゆえに、一般的には構成要件的同価値性を問うが、松宮説は結果を惹起し得るかどうかを論じているが、松宮自体、不作為の因果力を検討することは不可能として「準作為」なるものを観念しようとして不作為を「準作為」に置き換えていくわけである。私見は、救助的因果経過の遮断があるとしても、Xの行為後に父母の不作為や不保護があれば因果関係になる。(心理的に支配されているので、異常経過の介入ではなく、インスリン投与の阻止行為がまさに惹起したものであるから因果力も肯定されるので、準作為というまでもなく作為そのものと解するのが相当である。)
敷衍すると、一般的には、前田雅英の旧説によれば、実行行為に存する結果発生の確率の大小, 介在事情の異常性の大小, 介在事情の結果への寄与の大小の三要素を組み合わせて介在事情の寄与度が高くなく原因力が強い場合は因果力が肯定され「作為」として帰責されると説明されよう。
5 このように共同正犯との関係でXに不作為の殺人罪が成立するか、などを検討するのに先立ち、間接正犯が成立するのだろうか。
間接正犯とは他人をいわば道具として利用することにより、自ら犯罪を実行したのと同等の評価ができる場合に、利用者の正犯性を認めることをいう(最決平成9年10月30日)。
この点、①他人の意思を抑圧して利用する場合、②他人を錯誤に陥れて行為をさせる場合、③情を知らない他人を利用する場合―が典型例といえる。本件は、間接正犯でなければならないから正犯性、つまり自己の犯罪実現のための道具として利用したといえる必要がある。
本件ではXはYに対して、執拗かつ強度の働きかけを受けており、意思が抑圧されインスリンが評価できない精神状態と評価されたものと解される(最決昭和58年9月21日、最決昭和59年3月27日)。
以上のとおりYについては、被告人のインスリン不当よの指示こそ被害者の治癒につながると信じた故であり殺意はなく、父親は不保護の認識と認容はあったとされたものである。
6 本件ではXに犠律はあり得るとして、不作為の間接正犯なり、作為の間接正犯なり、作為の直接正犯なり、不真正不作為犯(不作為の直接正犯)のいずれかを利用して、Xに対して帰責させることができると考えるのが常識的かつ穏当といえる。
比較的手堅いのが、両親たちを共犯とするのであれば全員を共同正犯として行うものも実務上は手堅いといえるであろう。たしかにXは構成要件を一部行っているかは分からないが、重要な役割説からでも十分共同正犯は認めることができる。次に、間接正犯であるが、本件では当時12歳の養女を連れて巡礼中、日ごろ被告人の言動に逆らうそぶりを見せる都度顔面にタバコを押し付けたりドライバーで顔をこすったりするなどの暴行を加えて自己の意のままに従わせて窃盗をさせる事案に母親としては近いものと評価したものといえよう。
XはYにつき間接正犯の道具として利用することにより、自らの犯罪につき実行したのと同等の評価ができるから認定、評価の問題とはいえ間接正犯といえるだろう。私見も同様である。
7 なお松宮説は、Xの実行行為性は間接正犯により肯定するでもなく、また準作為ないし不作為として肯定する見解を否定的にとらえているようである。しかしながら、実行行為性は構成要件的結果発生惹起の現実的可能性が高まった場合に認められるのであるから、Xが治療費をもらい自己の犯罪として、構成要件的に同価値性の行為をしてVを殺せば、間接正犯ないし不作為の殺人罪が成立するように思われる。
松宮説はもともと不真正不作為犯が違憲であるから、作為犯の範疇を広げていたり準作為犯という概念があったりするのである。
しかし不作為犯には因果関係が認めずらいところがあるところ、松宮説は不真正不作為犯を否定していることから構成要件的同価値性があるか否かでは判断ができず、松宮説の問題は不作為犯は作為と同じような因果力を持てないという点がある。
一般的には、前田雅英の旧説によれば、実行行為に存する結果発生の確率の大小, 介在事情の異常性の大小, 介在事情の結果への寄与の大小の三要素を組み合わせて介在事情の寄与度が高くなく原因力が強い場合は因果力が肯定され「作為」として帰責されると説明されよう。
今日では、客観的帰属論を参考にして、因果力があるかを考察しているように考えられる。
例えば、①結果に対して第1行為がどれくらいの物理的因果を与えているか-である。物理的因果が強ければ文句なしで帰責して構わない。大阪南港事件がそうである。
次に,②物理的因果性が弱い場合には,第1行為が物理的に第2行為を誘発していないかを問うべきである。結局,「物理的」に第2行為を誘発したと評価できるのであれば,因果性を認めても構わないであろう。
次に,③同様に物理的因果性が弱い場合において,第1行為が心理的に第2行為を誘発するという場合である。この場合は,少なくとも心理的に強制している程度(意思の抑圧の程度といえる。)が問題とされるであろう。例えば,高速道路事件のように心理的強制が多ければ帰責も考えられるが,心理的強制の程度が弱ければ帰責は無理であろう。
ゆえに、松宮説からは、間接正犯と呼称しなくても物理的因果力が強い大阪南港事件のような①の場合、間接正犯ではなく作為の直接正犯と説明しているように思われる。松宮は作為につき、結果発生の相当程度の事実的危険性を持つ限り、作為の直接正犯であると指摘しているところである(上記①を見て欲しい、松宮も大阪南港に近づけて理解している。)が、これでは因果関係の先取りであるとの批判も生じるところであろう。
【参考文献】
前田雅英「未必的な殺意をもって、不保護の故意のある者と共謀の上、声明維持に必要な措置をさせず死亡させた者の殺人罪の成否」(ウェストロー判例コラム第211号)
藤井敏明「最高裁判所判例解説刑事篇」平成17年度184頁以下
松宮孝明「刑法総論講義第三版」(成文堂、2004年)
条解刑法第2版
【判例】
弁護人渡邊竜行の上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み,職権で判断する。
1 第1審判決及び原判決の認定並びに記録によれば,本件の経緯は,次のとおりである。
(1) 被害者(平成19年生)は,平成26年11月中旬頃,1型糖尿病と診断され,病院に入院した。1型糖尿病の患者は,生命維持に必要なインスリンが体内でほとんど生成されないことから,体外からインスリンを定期的に摂取しなければ,多飲多尿,筋肉の痛み,身体の衰弱,意識もうろう等の症状を来し,糖尿病性ケトアシドーシスを併発し,やがて死に至る。現代の医学では完治することはないとされるが,インスリンを定期的に摂取することにより,通常の生活を送ることができる。
(2) 被害者の退院後,両親は被害者にインスリンを定期的に投与し,被害者は通常の生活を送ることができていたが,母親は,被害者が難治性疾患である1型糖尿病にり患したことに強い精神的衝撃を受け,何とか完治させたいと考え,わらにもすがる思いで,非科学的な力による難病治療を標ぼうしていた被告人に被害者の治療を依頼した。被告人は,1型糖尿病に関する医学的知識はなかったが,被害者を完治させられる旨断言し,同年12月末頃,両親との間で,被害者の治療契約を締結した。被告人は,その頃,母親から被害者はインスリンを投与しなければ生きられない旨説明を受けるなどして,その旨認識していた。被告人による治療と称する行為は,被害者の状態を透視し,遠隔操作をするなどというものであったが,母親は,被害者を完治させられる旨断言されたことなどから,被告人を信頼し,その指示に従うようになった。被告人は,被害者の治療に関する指示を,主に母親に対し,メールや電話等で伝えていた。
(3) 被告人は,平成27年2月上旬頃,母親に対し,インスリンは毒であるなどとして被害者にインスリンを投与しないよう指示し,両親は,被害者へのインスリン投与を中止した。その後,被害者は,症状が悪化し,同年3月中旬頃,糖尿病性ケトアシドーシスの症状を来していると診断されて再入院した。医師の指導を受けた両親は,被害者の退院後,インスリンの投与を再開し,被害者は,通常の生活に戻ることができた。
しかし,被告人は,メールや電話等で,母親に対し,被害者を病院に連れて行き,インスリンの投与を再開したことを強く非難し,被害者の症状が悪化したのは被告人の指導を無視した結果であり,被告人の指導に従わず,病院の指導に従うのであれば被害者は助からない旨繰り返し述べるなどした。このような被告人の働きかけを受け,母親は,被害者の生命を救い,1型糖尿病を完治させるためには,被告人を信じてインスリンの不投与等の指導に従う以外にないと一途に考え,被告人の治療法に半信半疑の状態であった被害者の父親を説得し,同年4月6日,被告人に対し,改めて父親と共に指導に従う旨約束し,同日を最後に,両親は,被害者へのインスリンの投与を中止した。
(4) その後,被害者は,多飲多尿,体の痛みを訴える,身体がやせ細るなどの症状を来し,母親は,被害者の状態を随時被告人に報告していたが,被告人は,自身による治療の効果は出ているなどとして,インスリンの不投与の指示を継続した。同月26日,被害者は,自力で動くこともままならない状態に陥り,被告人は母親の依頼により母親の実家で被害者の状態を直接見たが,病院で治療させようとせず,むしろ,被告人の治療により被害者は完治したかのように母親に伝えるなどした。母親は,被害者の容態が深刻となった段階に至っても,被告人の指示を仰ぐことに必死で,被害者を病院に連れて行こうとはしなかった。
(5) 同月27日早朝,被害者は,母親の妹が呼んだ救急車で病院に搬送され,同日午前6時33分頃,糖尿病性ケトアシドーシスを併発した1型糖尿病に基づく衰弱により死亡した。
2 上記認定事実によれば,被告人は,生命維持のためにインスリンの投与が必要な1型糖尿病にり患している幼年の被害者の治療をその両親から依頼され,インスリンを投与しなければ被害者が死亡する現実的な危険性があることを認識しながら,医学的根拠もないのに,自身を信頼して指示に従っている母親に対し,インスリンは毒であり,被告人の指導に従わなければ被害者は助からないなどとして,被害者にインスリンを投与しないよう脅しめいた文言を交えた執ようかつ強度の働きかけを行い,父親に対しても,母親を介して被害者へのインスリンの不投与を指示し,両親をして,被害者へのインスリンの投与をさせず,その結果,被害者が死亡するに至ったものである。母親は,被害者が難治性疾患の1型糖尿病にり患したことに強い精神的衝撃を受けていたところ,被告人による上記のような働きかけを受け,被害者を何とか完治させたいとの必死な思いとあいまって,被害者の生命を救い,1型糖尿病を完治させるためには,インスリンの不投与等の被告人の指導に従う以外にないと一途に考えるなどして,本件当時,被害者へのインスリンの投与という期待された作為に出ることができない精神状態に陥っていたものであり,被告人もこれを認識していたと認められる。また,被告人は,被告人の治療法に半信半疑の状態ながらこれに従っていた父親との間で,母親を介し,被害者へのインスリンの不投与について相互に意思を通じていたものと認められる。
以上のような本件の事実関係に照らすと,被告人は,未必的な殺意をもって,母親を道具として利用するとともに,不保護の故意のある父親と共謀の上,被害者の生命維持に必要なインスリンを投与せず,被害者を死亡させたものと認められ,被告人には殺人罪が成立する。以上と同旨の第1審判決を是認した原判断は正当である。
よって,刑訴法414条,386条1項3号,181条1項ただし書,刑法21条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。