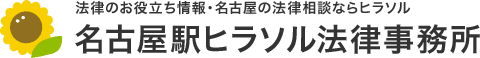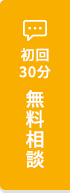【憲法学・行政学研究】生活保護訴訟~命の砦訴訟【大阪訴訟】(最判令和7年6月27日判例秘書登載)を巡って
【憲法学・行政学研究】生活保護訴訟~命の砦訴訟【大阪訴訟】(最判令和7年6月27日判例秘書登載)を巡って
目次
第1 生活保護訴訟-はじめに
平成25年5月、同26年3月、同27年3月、国は、生活保護費のうち食費や光熱費など日常生活を維持するための「生活扶助費」を最大1割切り下げ、約670億円を削減した。うち、570億円は厚労省が独自に「操作」して作出した物価下落率(4.78%)を踏まえた「デフレ調整」によるものだった。残りの約90億円は一般の低所得者世帯の生活水準などと比べて見直すという趣旨の「ゆがみ調整」が反映された。
本件は、大阪府内に居住する生活保護受給者である1審原告Xが、平成25年5月、同26年3月、同27年3月付厚生労働省告示による生活保護支給額の減額決定を受けた。
これに対してXは、3つの各決定の取消し及び国家賠償法1条1項に基づき国家賠償訴訟を求める訴訟である。
大阪地判令和3年2月22日は、3つの処分には厚生労働大臣の裁量権の逸脱・濫用があるとして3つの処分を取消し、減額に伴う精神的苦痛は処分が取り消され論理的に生活保護分の追加支給を得られることを理由に国家賠償請求を棄却した。
大阪高判令和5年4月14日は、本件減額の「改定」は次のような論理構造であると指摘した。金字塔を打ち立てた定年退官までに判決を出すという執念の宇賀克也裁判長反対意見の実質憲法25条違憲の歴史的判決の論点構造を検証したい。宇賀裁判長の上告審は処分取消を認めた第1審を維持し控訴を棄却する自判をして、国家賠償を棄却した2審の判断は結論において相当との多数意見を形成し、かかる部分についてはXの上告を棄却した。
本判決は、宇賀裁判官の裁量統制論に注目が集まりがちであるが、最高裁は、老齢加算を巡る最判(平成26年1月)では「財政事情」を削除していた。つまり、生活保護との関係では国の財政事情を独立の考慮要素として認めていなかったと考えられたが、本件上告審では、「国の財政事情を含めた多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察」として、あくまで一要素としてそのワーディングが復活しているところが気になるところである。学説の中には、デフレ調整については、それが生身の財政事情の反映ではなく、あくまで「需要」の測定に対応するものであることが論証されない限り、裁量権の逸脱濫用との評価を免れないとする見解もあった。
第2 宇賀克也裁判長の理論を巡って~二層による裁量統制論
1 憲法98条2項と裁量統制論の再構成
伝統的な行政裁量統制論は、専ら裁量権の逸脱・濫用があるかという社会観念審査といわれるものであった。
すなわち、憲法上、「積極目的」に該当するものについては行政庁の政策的裁量に属し、裁判所はその専門技術的・政策的評価を尊重すべきものとされていたのである。
このため、裁判所の審査は上記の社会観念審査に留まっていた(生活保護訴訟では朝日訴訟が著名である)。
もっとも、行政裁量統制論では、判断過程統制論が生活保護基準の老齢加算廃止についても用いられるようになっている。つまり、裁量があったとしても、裁量の具体化は高度の専門技術的な考察及び政策的判断を必要とするので厚生労働大臣には専門技術的かつ政策的見地からの裁量権が認められるとし、専門委員会の検討などの老齢加算の廃止に至る事実関係を前提としたうえで、厚生労働大臣の「判断の過程及び手続に過誤、欠落があると解すべき事情」の有無を問題視しているのである(最判平成24年2月28日民集66巻3号1240頁。塩野宏『行政法Ⅰ』109頁及び149頁(有斐閣、2020年))。
前掲塩野109頁は裁量統制論においても、生活保護法は委任の範囲が広すぎるため、判断過程の統制といっても形式的審査になってしまっていると批判している。塩野教授は日光太郎杉事件東京高裁判決を引用するが、最高裁においても、日光太郎杉事件判決の論理を採りつつも、社会観念審査を行っている例もある(小田急高架訴訟上告審判決)。
もっとも、第三小法廷は、合憲性判定基準にようなルールを定立し、合理的関連性や専門的知見との整合性があり、仮にその特定の偏頗な基準を用いるのであれば、過去の基準との整合性も専門的知見からアカウンタビリティを負うところ、そのような説明がないとして、実質的には憲法25条1項に違反しているかのような判断をしている。
すなわち、第三小法廷は、「合理的関連性や専門的知見との整合性を有するものというためには、上記限界を踏まえてもなお物価変動率のみを直接の指標とすることが合理的であることにつき、物価と最低限度の消費水準との関係や、従来の水準均衡方式による改定との連続性、整合性の観点を含め、専門的知見に基づいた十分な説明がされる必要がある」としており、合理的関連性のテストや過去用いてきた手法との論理的整合性との説明責任を果たさない限り、違法であるとしている点が新たな裁量統制論といえる[1][2]。
2 宇賀克也裁判長の新たな裁量統制論
- ⑴ 宇賀裁判長の最判令和7年6月27日第三小法廷の反対意見は、実質は国家賠償請求を認めるか否かで反対意見になっているに過ぎず、行政処分との取消しとの関係では、憲法論から新たな裁量統制論を導入するものとなっている。
- ⑵ 反対意見は、従来の「社会観念審査」「日光太郎杉事件の判断過程審査という裁量統制論」に加えて、行政法学的技術を媒介としつつ、国際人権法の立場からのアカウンタビリティを持ち込んで裁量統制を図ったものである。
- ⑶ 宇賀裁判長は、生活保護法8条2項の「最低限度の需要を満たすに十分なもの」イコール憲法25条1項の「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」との定式を示し憲法25条1項の問題にすることを意図的に回避し、朝日訴訟や堀木訴訟とは異なるアプローチを採用することを示す。
- ⑷ そして、宇賀裁判長は、法廷意見とは異なり、「高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断」を必要とすると指摘している。すなわち、宇賀裁判長が示す「社会観念審査」「判断過程審査」に加えて、「専門的合理性を欠き説明責任が尽くされない場合は生活保護法8条2項(=ひいては憲法25条1項)に違反するという判断枠組みを提示している。
- ⑸ 憲法25条1項の合憲性判断基準を厳しいものを採用するのではなく、あえて朝日訴訟や堀木訴訟がある憲法25条1項を回避し、憲法98条2項から社会権規約2条1項を結合させている。そして、宇賀裁判長は、批准されて国内法でも通用力がある社会権規約の条約の法が個別法より上位にあると位置づけているように思われる。
- ⑹ 反対意見は、憲法25条1項の権利性を問題にすることなく、社会権規約自体が国民に直接の請求権を与えるわけではないとしながらも、憲法98条2項の下でその効力は国家機関を拘束するとしている。
- ⑺ そのうえで、宇賀裁判長は、社会権規約に基づき「国は、保護基準の引下げがやむを得ないことについて、説得力ある説明を行う必要がある」と指摘し、説明責任の履行を憲法から導き、「専門的合理性を欠き社会権規約との関係で説明責任が尽くされない場合憲法的義務違反として違法」とする第三の層の裁量統制論を構築したものといえる。
- ⑻ 宇賀裁判長のロジックで引用されるICESCR2条1項は、端的にいうと、①現在有するリソースを最大限活用し、②時の経過とともに着実に逆行せず、③後退的措置をとる場合は十分な正当化根拠を説明せよとの努力義務及び説明義務が組み合わされている。宇賀裁判長は、上記③の後退的措置について、社会権規約の監視組織CESCRは、「制度後退禁止原則」(いかなる意図的な制度後退であっても、それを正当化する強い説明が必要である)があるとしていると指摘しているように思われる。
すなわち、宇賀裁判長は、ICESCR2条1項では、原則として逆行は禁止され後退的措置をとる場合の説明責任に着目し、これを国内法秩序において「政策決定過程における説明責任義務」として翻訳したものと解される。
したがって、憲法98条2項は、生活保護法の分野で国際的義務を国内憲法秩序における行政裁量統制論の根拠条文として接続して、後退的措置の正当化根拠と説明責任と整理されたものと思われる。
- ⑼ 宇賀裁判長が援用するICESCR2条1項はあくまで努力義務と説明責任が課されたものであるため、裁量統制論は、憲法上の説明義務の履行審査へと質的に変容することになる。(もっとも、生活保護の切り下げ処分をする時点での説明義務の履行が問題になるが、現実には、裁判所が審査するほかないようにも思われる。)
- ⑽ 宇賀裁判長反対意見では、生活保護基準が逆行するとき、「専門的合理性の論証」「外部専門家の意見聴取」「統計的根拠の開示」を怠れば、それは行政手続に違反したのみならず、憲法98条2項に基づく説明義務違反として、裁量逸脱があると評されることになる。なお、例えば女子差別撤廃条約(CEDAW)やこどもの権利条約(CRC)は、個人に直接的適用され裁判規範性があり、裁判規範において直接又は間接に援用可能であるのに対して、ICESCRは直接請求権は国民にはなく斬新的実現義務しかないことから、宇賀裁判長は「逆行」というポイントと憲法98条2項を持ち出しているものと思われる。つまり、国内での裁判規範性が弱い場合に「弱い条約を国内審査枠組みに入れる司法回路」として活用しているように思われる。
- ⑾ 宇賀裁判長は、朝日訴訟や堀木訴訟の社会観念審査に阻まれることが多い生活保護訴訟について、裁量統制論をこれまでの裁量統制論を進化させ「憲法的説明義務統制」というロジックを編み出したものといえる。
- ⑿ 本判決は、専門的知見との整合性という観点からドイツ法の首尾一貫原則に近しいロジックを導くため、憲法98条2項を経由し社会権規約を導入し、より厳しい説明責任を課したものといえる。また、前掲塩野94頁において、近時における行政改革の過程で、行政法上の基本原理として行政の公正・透明性の原則、説明責任の原則があると解説されていることと親和的であり、社会権であるから裁量が広いというロジックは困難になっていると思われる。
- ⒀ このような宇賀裁判長の条約を憲法98条2項という中間項を挟むという展開により国家に説明責任の履行を迫るというのは伝統的に憲法審査が弱いとされていた事項、社会保障、医療、環境、女子差別、こどもの権利などの多様な政策テリトリーにおける「憲法的行政裁量統制論」を取り入れるものである。
- ⒁ 伝統的行政法である前掲塩野から、学説は、行政の公正・透明性の原則は主に行政手続法上の基本原理として、説明責任の原則は、主に情報公開法の原則として捉えられるものの、より広く行政作用一般にかかる嚮導的法理【司法判断や制度運用の方向性・基本理念を先導するような法的原理】といえるとされていた。判断過程審査論では審査手法を裁判所がなし得るのは行政庁としてはいかなる情報に基づいていかなる見地に立って判断したかを説明する責任があるという政府の説明責任の原則からの根拠付けも可能」(152頁)とされていたが、いささか前掲塩野は叙述の割に論拠は行政改革と説明されるにとどまっていた。
- ⒂ 情報公開法を専門とする宇賀裁判長が上告審をリードしたことからも、「近時における行政改革の過程」だけでは論拠が弱いように思われたことから、裁量統制論のうち判断過程論の二階層化を試みたものとみられる(94頁)。
- ⒃ 新たな裁量統制の論拠の萌芽が憲法98条2項及び社会権規約により論拠付けられたことは宇賀克也裁判長の正しく「憲法判例」としての有終の美であったといえよう。加えて、生活保護訴訟において朝日訴訟は原告死亡の傍論として述べられたものに過ぎず判例に該当しないことや30年間継続した水準均衡方式導入前の意見であることから先例価値がないこと、堀木訴訟は立法府の立法裁量について述べたものであり、厚生労働大臣の生活保護基準定立の先例にならないことを明らかにして、老齢加算廃止最高裁訴訟は、実質的に判断過程審査もあり、実質的に判例変更があったと理解し、上告審は老齢加算廃止訴訟の最高裁判決しか引用しておらず、悪名高き朝日訴訟及び堀木訴訟の判例としての価値も失わせた点が高く評価できると考えられる。
第3 争点
1 ゆがみ調整規定
- ⑴ そもそも、自民党が選挙の際生活保護を切り下げることを公約にしたわけであるから、理論的な理由はないように思われる。ゆがみ調整には「地域級地別指数」、「世帯人員別指数」、「年齢別指数」がある。
- ⑵ 地域級地別指数は「裁判官の地域手当」であり都市部ほど物価が高く地方部ほど物価が安いという論理に基づいているが、実際、生活実感からすると、東京都でも名古屋市でもそれほど物価が変わるとは思えない。むしろ、家賃を除くと東京都内の方が物価が安いというデータもある。もっとも、厚生労働省の告示により、地域級地別指数は切り下げの理由にはされなかったことから、訴訟の争点とはならなかった。
- ⑶ 世帯人員指数というのは、世帯が増えると、家賃、食費などが効率化するから、世帯の人数が増えても逓減させるというものである。一例を挙げると、一人目は100、二人目は70、三人目は50といったものである。しかし、理論的にはそのようにいえるかもしれないが、現実的に一人目のこどもの指数が100であるのに三人目の指数を50とするのは家庭裁判所の標準算定方式とも異なる。結果、母子家庭などの子育て世帯を直撃することになったのである。
- ⑷ 「年齢別指数」というのは「高齢者」と「若者」について、厚生労働省は、高齢者は医療費、暖房費、日用品費が多くなるので指数が高いが、若者にはそのような事情はないとして、高齢者は据え置く一方で若者については減額する措置をとった。しかし、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条)について、若者が医療費が少なく、暖房費が安く、日用品費も安いというエビデンスは認められない。むしろ、家庭裁判所の標準算定方式から考えると、15歳以上はほぼ大人と同じ生活費がかかるのであって、統計的データに基づかないフェイクニュースのような論拠と言わざるを得ない。
2 デフレ調整規定
デフレ調整規定は、「物価の下落」を考慮して、一般世帯との関係における扶助基準の水準を是正しようとする部分である。
確かに、平成25年5月、同26年3月、同27年3月にデフレ基調といえるのであれば通貨の価値が上昇しているのであるから、名目支給額を減額させたとしても不合理とはいえない。
しかし、総務省統計局の消費者物価指数によれば、前年度プラスになっており、平成25年についてはデフレ基調といえるほどの物価の下落は認められていない。一例を挙げると、水道光熱費は4.6パーセントの上昇が総務省の統計から認定できる。
上記のように、平成25年の平均CPIの変動率は0.4パーセントであり、横ばいの基調であり、物価が下落しているという事実はない。また、平成26年のCPIは2.7プラス、平成27年は0.8プラスであり、むしろインフレ基調にあったのではないかとすら推認することができる。
したがって、客観的にデフレを根拠に生活保護基準を引き下げることは合理的とはいえない。
3 激変緩和措置
激変緩和措置は代償措置のことであるが、激変緩和措置により、「ゆがみ調整」及び「デフレ調整」による急激な生活保護費の減額を「2分の1」に留めてあげるというものである。このように実際はもっと減らされても文句はいえないが、2分の1にしてあげたのだ、ありがたいであろうというのが代償措置論である。
ある意味、激変緩和措置(代償措置)により減額は2分の1までという減額のキャップが被せられたことにはなり、結果、多くは改定による基準生活費の減額は10パーセントにとどまるよう制度設計された。
4 訴訟上の争点
争点は、①本件改定にかかる厚生労働大臣の判断に裁量権の逸脱・濫用があるか、②3つの減額改定決定が行政手続法14条1項本文の規定する理由の提示に欠くものであるか、③国家賠償法上精神的苦痛は賠償の対象か―にある。
5 原審の判断
大阪高判令和5年4月14日は、ゆがみ調整、デフレ調整及び激変緩和措置について、特にデフレ調整の適法性は原告及び被告国の攻撃防御が最も集中したといえる。なぜなら、世帯人員指数は個別世帯の逓減の問題にとどまり主に母子家庭のうち多子家庭が問題になるに過ぎないのに対して、デフレ調整規定は、一律4.78パーセントを減少させるインパクトを持ったからである。
大阪高裁は、堀木訴訟を引用し明白性の原則のような幅広い裁量を厚生労働大臣に与え全て適法とされた。X上告。
6 上告審
破棄自判。一部控訴棄却。一部上告棄却。宇賀克也裁判官反対意見。
―法廷意見
- ⑴ 第三小法廷は、「生活保護法3条によれば、同法により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないところ、同法8条2項によれば、保護基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつ、これを超えないものでなければならない・・・最低限度の生活は、抽象的かつ相対的な概念であって、その具体的な内容は・・・同条1項の委任を受けた厚生労働大臣がこれを保護基準において具体化するに当たっては、国の財政事情を含めた多方面にわたる複雑多様な、しかも高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断を必要とするものである。そうすると、厚生労働大臣は、生活扶助基準を改定するに当たり、それにより基準生活費を減額されることとなる被保護者の期待的利益についての配慮の要否等を含め・・・専門技術的かつ政策的な見地からの裁量権を有しているもの」ものとした。
- ⑵ そして、「本件改定は、その判断に上記見地からの裁量権の範囲の逸脱又はその濫用がある場合に、生活保護法3条、8条2項に違反して違法となる・・・生活扶助基準の改定の要否の判断の前提となる最低限度の生活の需要に係る評価や被保護者の期待的利益についての配慮は・・・専門技術的な考察に基づいた政策的判断であるところ、これまでも生活扶助基準の改定に際しては、専門家により構成される合議制の機関等により、各種の統計や資料等に基づく専門技術的な検討がされてきたところである・・・厚生労働大臣の上記の裁量判断の適否に係る裁判所の審理においては、主として本件改定に至る判断の過程及び手続に過誤、欠落があるか否か等の観点から、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無等について審査されるべきもの」と解される。
- ⑶ 「ゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断についてみると、本件において、平成25年検証の結果に統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところ」はなく、「児童のいる世帯への減額の影響が大きくなることが見込まれており、生活扶助基準の見直しを具体的に検討する際には児童のいる世帯への影響に配慮する必要があるともされていた」から、「その反映に当たり減額率を限定することには合理性があるということができる。また、ゆがみ調整が、生活保護受給世帯間の公平を図るため、生活扶助基準における展開のための指数を適正化することを目的とするものであることに照らせば、減額率に合わせて増額率を限定することにも一定の合理性がある」とした。そのうえで、激変緩和措置も踏まえると、「ゆがみ調整における改定率を平成25年検証の結果をそのまま生活扶助基準に反映する場合の2分の1に限定したことが不合理であるともいえない」し、「2分の1処理に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」といえず、「2分の1処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところはなく」適法とした。
- ⑷ 「生活保護法8条2項は、保護基準は、保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすものとすべき旨を規定しているところ、ここにいう『最低限度の生活の需要を満たす』とは、生活扶助については、最低限度の消費水準を保障することを意味するものとして理解されてきた・・・水準均衡方式も、当時の生活扶助基準が、一般国民の消費実態との均衡上、最低限度の消費水準を保障するものとしてほぼ妥当なものとなったとの評価を前提として、一般国民の消費動向を踏まえると同時に、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図る方式により生活扶助基準を改定していくことによって、一般国民の消費実態との関係において妥当な生活扶助の水準を維持しようとするもの」とした。
- ⑸ これに対し、「物価は、これが変動すれば消費者の消費行動に一定の影響が及ぶとは考えられるものの、飽くまで消費と関連付けられる諸要素の一つにすぎず、物価変動が直ちに同程度の消費水準の変動をもたらすものとはいえない・・・賃金や物価は、そのままでは消費水準を示すものではないので、参考資料にとどめるべきものとされているところである。平成15年中間取りまとめでは、生活扶助基準の改定方式の在り方に関し、改定の指標についても検討が必要であるとされ、例えば、消費者物価指数の伸びを改定の指標の一つとして用いることも考えられるとされているが、これも、物価変動率を考え得る指標の一つとして例示し、その検討の必要性に言及したにすぎないものと解される・・・平成25年検証の結果を踏まえて生活扶助基準の見直しを検討する際に、他に合理的説明が可能な経済指標を総合的に勘案する場合があり得ることを前提とする記載があるところ、ここにいう経済指標に物価変動率が含まれるとしても、それは総合的に勘案する指標の一つに位置付けられているにすぎないし、平成25年報告書も、これを勘案する場合にはその根拠を明確に示すべきことを求めている。現に、本件改定前において、物価変動率のみを直接の指標として生活扶助基準の改定がされたことはなかった」とした。
- ⑹ 以上に述べたところによれば、「物価変動率(筆者注:第三小法廷がいう「物価変動率」というのは消費者物価指数(CPI)とは異なり、厚労省がマニピュレートした生活保護世帯が使いそうな品目に恣意的に絞り込んだ捏造された物価変動率のことをいう)は、生活扶助基準の改定の際の指標の一つとして勘案することが直ちに許容されないものとはいえないとしても、それだけでは消費実態を把握するためのものとして限界のある指標である」といわざるを得ず、「不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標として基準生活費の改定率を定めることが、統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を有するものというためには、上記限界を踏まえてもなお物価変動率のみを直接の指標とすることが合理的であることにつき、物価と最低限度の消費水準との関係や、従来の水準均衡方式による改定との連続性、整合性の観点を含め、専門的知見に基づいた十分な説明がされる必要があるというべき」である。
- ⑺ しかるに、「国らは、消費者物価指数の伸びも改定の指標の一つとして用いることも考えられるとされていたこと等を挙げて、物価変動率のみを直接の指標として用いても専門的知見と整合しないものではないなどと説明するにすぎず、上記不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標として用いることが合理的であることについて、専門的知見に基づいた十分な説明がされているということはできない」とした。。
- ⑻ そして、「物価変動率を指標とすることが、一般論としては専門的知見と整合しないものではないからといって、それまで水準均衡方式によって改定されてきた生活扶助基準を、物価変動率のみを直接の指標として改定することが直ちに合理性」を有しないところ、「不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標として用いることについて、基準部会等による審議検討が経られていないなど、その合理性を基礎付けるに足りる専門的知見があるとは認められない」というべきである。
- ⑼ そうすると、デフレ調整における改定率の設定については、上記不均衡を是正するために物価変動率のみを直接の指標として用いたことに、専門的知見との整合性を欠くところがあり、この点において、デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったものというべき」である。
- ⑽ 以上によれば、本件改定は、物価変動率のみを直接の指標としてデフレ調整をすることとした点において、その厚生労働大臣の判断に裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法3条、8条2項に違反して違法というべきである。
-
⑾ ゆえに、「Xの保護変更決定の取消請求に関する原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する論旨は以上の趣旨をいうものとして理由があり、原判決のうち上記請求に関する部分は破棄を免れない。そして、既に説示したところによれば、上記請求に係る保護変更決定は違法というべきであり、上記請求を認容した第1審判決は正当であるから、同部分につき国各市の控訴を棄却すべき」である。
-
-宇賀克也裁判官反対意見
- ⑴ 私は、原判決のうち保護変更決定の取消請求に関する①原審のデフレ調整に関する判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとする多数意見の結論及び理由に賛成し、その理由を補足して意見を述べるとともに、多数意見のうち、②ゆがみ調整の2分の1処理に違法はないとする部分及び本件改定につき国家賠償法1条1項にいう違法があったとはいえないとする部分については、意見を異にするので、その理由について述べる。
- ⑵ 本件訴訟では、国民感情、財政事情、与党の政権公約という生活保護法8条2項で例示されていない事項が、「その他保護の種類に応じて必要な事情」に当たるかが、争点になっている。上記の事項が「その他保護の種類に応じて必要な事情」に含まれ、政策的裁量として考慮事項になり得るとしても、生活保護法8条2項は、「最低限度の生活の需要を満たすのに十分なもの」である保護基準の策定を厚生労働大臣に義務付けているのであるから、多数意見の参照する最高裁平成24年2月28日第三小法廷判決及び最高裁平成24年4月2日第二小法廷判決が判示するように、保護基準の改定に当たっては、「高度の専門技術的な考察とそれに基づいた政策的判断」を必要とする。
- ⑶ したがって、まずは、専門技術的判断の部分について判断過程審査を行い、その部分で判断過程の過誤、欠落が認められれば、政策的判断の部分の適法性に立ち入るまでもなく、本件改定に基づく保護変更決定は、裁量権の逸脱・濫用として違法となると考えられる。
- ⑷ 憲法98条2項の規定により、条約は公布とともに国内的効力を有し、国家機関である立法機関、行政機関及び司法機関にはその効力が及ぶ。社会権規約2条1項等は、国民に対する直接適用可能性はないと考えられるし、国が保護基準を引き下げることを一律に禁止するものではないが、国は、その引下げがやむを得ないことについての説得力ある説明を行う必要があるという解釈を基礎付けるものといえる。
- ⑸ 保護基準の改定は、専門技術的な検討を要することから、従来、専門機関の検討を経たうえで、その結果に基づき行われてきた。
しかし、本件では、ゆがみ調整の2分の1処理及びデフレ調整を行うことについて、基準部会の意見を聴取しておらず、厚生労働省内部で判断がされており、事前に社会保障審議会にも知らされていなかった(むしろ部外秘扱いとされ秘匿されていた。)。この点については、保護基準の改定に当たり、社会保障審議会(基準部会)の意見聴取を義務付ける明文の規定は存在しないので、基準部会の意見を聴取しなかったことが、直ちに、本件改定の違法性につながるとまではいえないと考えられる。
もっとも、基準部会の検討結果に基づく改定の場合には、基準部会における判断過程を審査し、そこに合理性が認められれば、その検討結果を尊重して行った厚生労働大臣の改定の合理性も基本的には肯定されることになると思われるが、他方、ゆがみ調整の2分の1処理及びデフレ調整について外部有識者による専門機関の関与がない本件の場合には、厚生労働省内部において、いかなる資料に基づき、いかなる判断過程を経て、そのような処理がされたのかについて、国らには、統計等の客観的な数値との合理的関連性や専門的知見との整合性等について主張立証する必要が生ずることになり、判断過程審査においては、この点について十分な審査が行われる必要がある。
- ⑹ 厚生労働省内部でゆがみ調整における2分の1処理が検討されたのは、基準部会が平成25年報告書を取りまとめる前であった。基準部会で2分の1処理が検討されていなかったにもかかわらず、厚生労働省内部で、2分の1処理が妥当と考えたのであれば、その根拠を示して基準部会の意見を聴取し、その結果を平成25年報告書に反映させることが可能であり、かつ望ましいと考えられるところ、基準部会の意見を聴取することは容易であったにもかかわらず、なぜ、そのような対応をしなかったのかについて、国らは、政策的判断であると述べるのみで、具体的理由を明らかにしていない。他方、平成25年報告書の取りまとめに先立ち行われた平成25年1月における厚生労働省担当者と内閣官房副長官との協議では、本件改定を行うことにより財政削減効果がある旨が記載されていたが、この文書は取扱厳重注意とされ、対外的には公にされず、行政文書開示請求を受けて開示されて、初めてその内容が明らかになった。
- ⑺ 多くの生活保護受給者に重大な影響を与える2分の1処理の必要性と根拠については、行政の説明責任があるはずであるにもかかわらず、なぜ、それを基準部会にも国民にも秘匿する必要があったのかについても、説得力ある説明はなされていない。
- ⑻ 後に、国らは、2分の1処理の理由は激変緩和措置であると説明するようになったが、ゆがみ調整の結果、生活扶助を減額される者にとっては、2分の1処理は激変緩和措置といえても、増額される者にとっては増額分を減少させられることになるから、激変緩和措置とはいえず不利益な措置となる。したがって、2分の1処理の理由は激変緩和措置であるとする国らの説明には疑問がある。
- ⑼ もっとも、ゆがみ調整を行うと、保護基準が引き下げられる世帯の方が多く、特に児童のいる世帯への減額の影響が大きいとされ、2分の1処理を行うことが、ゆがみ調整の結果、減額となる児童のいる世帯にとっては、激変緩和措置としての意味を有するということはいえる。しかし、すべて国民は、生活保護法の要件を満たす限り、同法による保護を無差別平等に受ける権利を有するのであり(同法2条)、児童のいる世帯を優遇するために、児童のいない世帯が不利益を受ける措置を正当化することができるのかという疑問が生ずる。
- ⑽ ゆがみ調整の結果、減額となる世帯のための激変緩和措置として2分の1処理が正当化されるとしても、激変緩和措置であれば、減額世帯のみを対象として行えばよく、増額世帯に2分の1処理を行うことの合理性にも疑問が残る。他方、ゆがみ調整の結果、減額となる世帯についてのみ2分の1処理を行えば、新たなゆがみが生ずるので、生活保護受給世帯間の公平を図るというゆがみ調整の趣旨に適合しないのではないかという疑問も生ずる。
- ⑾ しかし、判断過程審査は、判断過程の過誤、欠落を審査するものであり、そのような司法審査を行うことによって、行政裁量の行使が適正な過程で行われることを促す意義も有する。本件の2分の1処理が行われた過程が、極めて疑問の残るものであることに鑑みれば、2分の1処理についても、判断過程に過誤があると解すべきと考える(ゆがみ規定も違法との反対意見)。
- ⑿ デフレ調整が本件訴訟で大きな争点になった理由は、①生活扶助基準の改定については、従前、基準部会等の専門機関の検討を経てきたにもかかわらず、本件のデフレ調整は基準部会等の専門機関の検討を経ずに厚生労働省内部での検討のみで行われたこと、②平成19年報告書によれば、生活扶助基準が一般低所得世帯の消費実態に比べて高くなっていたとされているが、その程度はわずかといえ、平成19年検証後の社会経済情勢や物価の動向、特に食料費や光熱水費といった一般低所得世帯の家計に重要な費目に係る物価はむしろ上昇していることに照らし、平成23年までに生活扶助基準が一般低所得世帯の消費実態と比較して高くなっているとはにわかに認めがたいこと、③従前、生活扶助基準の改定は、昭和58年意見具申に基づき水準均衡方式で行われてきたが、本件のデフレ調整は、物価変動率を単独で直接の指標とする新しい方法であり、本件改定前に、物価変動率を単独で直接の指標として保護基準の改定がされた例がないにもかかわらず、物価変動率を単独で直接の指標とすることの合理性を裏付ける統計や専門家の作成した資料があるという事実はうかがわれないこと、④物価変動率を算定するに当たり、一般に用いられている消費者物価指数(総務省CPI)によらず、厚生労働省職員が本件で独自に作成した生活扶助相当CPI(いわば「捏造のCPI」)を用いたことにより物価の下落率が著しく大きく算定されたこと(総務省CPIを用いると物価下落率は2.35%、生活扶助相当CPIを用いると物価下落率は4.78%と2倍以上になる。)等、多岐にわたる。
- ⒀ このうち、①については、専門機関の検証を経なかったことが直ちに違法とまではいえないが、常設の基準部会が存在する以上、その意見を聴取することは容易であり、それを省く必要があるほどの緊急性があったわけではなく、従前、基準部会の意見を聴取してきた経緯に照らしても、本件で、基準部会の意見を聴取しなかったことについての合理的説明が、国らによってなされる必要がある(生活保護基準の切り下げには基準部会の意見聴取をすべきでそれをしない場合は高度の合理的説明が求められる)。
- ⒁ ②については、まずもって、生活保護法8条2項の規定に着目する必要がある。なぜならば、厚生労働大臣が生活扶助基準を定めるに当たっては、「最低限度の需要を満たすに十分なもの」とすることが義務付けられているからである。厚生労働大臣が、生活扶助基準の作成に当たり行政裁量を有するといっても、行政裁量は法律が許容する範囲内でしか認められず、法律に違反した生活扶助基準を定めれば、その生活扶助基準は、委任の範囲を逸脱して違法となることはいうまでもない。
- ⒂ 「最低限度の需要を満たすに十分なもの」とは、昭和55年の「生活保護専門分科会審議状況の中間的とりまとめ」で述べられているように、最低限度の需要を満たす消費を行うのに十分なものであること、すなわち、最低限度の消費支出を保障することを意味する。
- ⒃ 厚生労働大臣が被保護者に対する給付額を引き下げる方向で保護基準を改定するためには、「最低限度の需要」が縮小したことが要件になり、その要件を満たすことを国らが立証する必要がある。したがって、国らによって、この立証責任が果たされているかを検証する必要がある。
- ⒄ ③については、水準均衡方式が昭和58年意見具申に基づき昭和59年から採用され、約30年という長期間にわたって用いられてきたのも、「最低限度の需要を満たすに十分なもの」を算定するためには消費に着目するのが最も適切であるからといえる。物価変動は消費行動に一定の影響を及ぼし得るが、消費に影響を与える一要素にすぎず、物価変動が直ちに同程度の消費実態の変動をもたらすわけではない。そのため、昭和58年意見具申でも、賃金や物価は、そのままでは消費水準を示すものではないので、参考資料にとどめるべきとされたのである。平成15年中間取りまとめでは、保護基準の改定に当たり消費者物価指数(総務省CPI)の伸びを改定の指標の一つとして用いることも考えられるとされていたが、その利用を積極的に推奨する趣旨ではなく、検討の必要性を指摘したにすぎない。平成25年報告書においても、物価の位置付けは、総合的に勘案する指標の一つにすぎないとされている。したがって、本件改定に当たり、物価変動率(捏造されたCPI)を単独で直接の指標として用いることの合理性について、専門的知見に基づく説明が国らによりなされる必要がある。
- ⒅ この点についての国らの説明では、本件改定に当たりいかなる指標を用いるかは、厚生労働大臣の専門技術的かつ政策的見地からの裁量に属し、平成15年中間取りまとめで「消費者物価指数の伸びも改定の指標の一つとして用いることなども考えられる」とされていたことが挙げられている。しかし、保護基準の改定に当たり厚生労働大臣に政策的判断の余地があるとしても、前掲各最高裁判決が判示するように、それは「専門技術的な考察に基づいた政策的判断」でなければならないから、専門技術的な判断が先行しなければならない。しかし、国らの以下の説明は、専門機関により推奨された水準均衡方式に代えて、物価変動率を単独で直接の指標として用いることの専門技術的合理性を説明できていないといわざるを得ない。すなわち、国らの説明のうち、①平成21年全国消費実態調査によれば、夫婦子1人の一般低所得世帯の消費水準が平成16年全国消費実態調査から約11.6%下落しており、平成19年検証時点における同世帯の生活扶助基準額を約12.6%下回る状況になっていたから、消費を基礎とすると減額幅がより大きくなったと想定されるという主張は、「一般低所得世帯」の消費水準との比較によるものであるところ、国ら自身が、「最低限度の生活」は「一般国民」の生活水準との相関関係で捉えられるべきと強調していることと符合しない。現在も用いられている水準均衡方式の下では、一般国民の生活水準との比較を行っており、一般低所得世帯の消費水準との比較を行っているわけではないから、一般低所得世帯の消費水準との比較を根拠とする国らの主張の合理性は認め難い。しかも、①の主張は、平成16年全国消費実態調査から平成21年全国消費実態調査までの変化を問題にするものであって、本件改定時における大幅な生活扶助水準の引下げを正当化する根拠とはいい難い。また、国らの説明のうち、②平成29年検証の結果、本件改定後の夫婦子1人世帯における生活扶助基準額が一般低所得世帯の消費水準とおおむね均衡することが確認されたと評価されており、デフレ調整の妥当性が裏付けられているという主張については、やはり、一般低所得世帯の消費水準との比較を根拠としており、上記①について述べたように、合理性を認め難い。
以上を要するに、本件のデフレ調整については、④等について検討するまでもなく、判断過程に過誤、欠落があり、違法と評価せざるを得ないと考える。 - ⒆ ゆがみ調整の結果、標準世帯の生活扶助基準額に影響が及んでいることとデフレ調整との関係について専門技術的見地からの検討が行われたとは認められないところ、ゆがみ調整とデフレ調整を併せて行うことの影響を検討することは当然といえるが、それが行われた形跡がないため、ゆがみ調整とデフレ調整の併用についても、判断過程に過誤、欠落があり、違法と評価せざるを得ないと考える。
- ⒇ 本件改定に当たり、ゆがみ調整の2分の1処理及びデフレ調整については、専門機関の意見を聴取していないのみならず、厚生労働省内部でも、統計や専門的知見と整合する検討が行われた形跡をうかがうことはできない。とりわけ、専門機関の推奨を受けて長年にわたり用いられてきた水準均衡方式に代えて、物価指数のみを単独で直接の指標とする改定を行ったことは明らかに違法といわざるを得ないと思われる。なぜならば、昭和58年意見具申では、「賃金や物価は、そのままでは消費水準を示すものではないので、その伸びは、参考資料にとどめるべき」とされ、平成16年報告書では消費者物価指数が補充的指標となり得るとの指摘すらなく、平成25年報告書では、他の合理的説明が可能な経済指標等を総合的に勘案する場合には、その根拠について明確に示し、見直しの影響に慎重に配慮すべき旨の指摘がされていたにもかかわらず、昭和58年意見具申を受けて約30年間にわたり一貫して用いられてきた水準均衡方式に代えて、前例のない物価指数単独の指標を用いるのであれば、常設の基準部会の意見を聴取すべきであり、それが困難であったとみるべき事情は見当たらない。また、基準部会の意見を聴取しないのであれば、厚生労働省内で、専門技術的検討が十分に行われるべきであったのに、それが行われた形跡は見当たらない。
さらに、物価変動率を算定するに当たり、生活扶助相当CPIを用いるということは、最低限度の生活を営むのに必要な費用の減少割合が一般的世帯よりも被保護者世帯の方が大きいことが前提となるところ、それを裏付ける統計や専門家の作成した資料があるという事実はうかがわれない。生活扶助相当CPIの算出過程については、社会保障生計調査の結果によれば、被保護者世帯の教養娯楽に属する品目に対する支出の割合が一般的世帯よりも相当低いという客観的な数値を見いだし得る以上、その特徴に整合するよう専門的知見を駆使した形で生活扶助基準の改定をすべきであったのに、それがされていないため、教養娯楽に属する品目、とりわけ教養娯楽用耐久財(テレビ、ビデオレコーダー、パソコン等)の物価の大幅な下落の影響が増幅されていること、世界的な原油価格の高騰や穀物価格の高騰を原因として石油製品を始め、多くの食料品目の物価が上昇し、消費者物価指数が11年振りに1%を超えた特異な物価上昇があった平成20年を物価変動率の起算点としたため、同年からの物価下落率が大きくなっているが、生活扶助基準が平成17年度以降本件改定に至るまで改定されていなかったことに鑑みれば平成17年との比較がより合理的なこと、ゆがみ調整においては、平成21年の全国消費実態調査の結果に基づいて改定率が定められていること等に鑑みると、平成20年を起算点とすることの合理性が説明できていないこと、物価指数の算定には伝統的にラスパレイス指数が用いられているところ、本件改定に当たっては、平成20年度から平成23年度にかけて、異なる算定方法(平成20年度から平成22年度については、平成22年度をウエイトの基準時にして物価指数を過去に遡及する形で計算するパーシェ方式、平成22年度から平成23年度は平成22年度をウエイトの基準時にして将来に向かって計算するラスパレイス方式)を用いたため、保護受給世帯には関係が希薄な電気製品の価格低下の影響が強く表れ、生活扶助基準額の引下げに寄与していることなどの問題がある。
また、本件改定以前に加算部分を除いた生活扶助基準の引下げが行われたのは2回のみで、いずれも1%未満(それぞれ0.9%と0.2%。)であったが、本件のデフレ調整による引下げは、3年間にわたり最大10%(年平均6.5%)、総額670億円に及び、期末扶助手当70億円も削減されたので、総額740億円(年平均7.3%)という大規模な減額であって、多人数世帯や子育て世帯ほど削減率が大きかったが、激変緩和措置として減額幅の上限を10%に設定したため、激変緩和措置の対象となった被保護者世帯は約2%にとどまり、被保護者世帯の期待的利益に可及的に配慮するという観点からも裁量権の逸脱・濫用と判断される可能性は否めないと思われる。そして、物価指数を用いる場合に総務省CPIではなく、国際的基準にも合致しない生活扶助相当CPIを用いたことについても、被保護者世帯の消費実態が生活扶助相当CPIと異なることは、統計等の客観的数値に真摯に向き合い、専門的知見に基づいて冷静に分析すれば探知できたはずである。
また、平成20年を物価下落率算定の起算点とすれば、同年の特異な物価上昇が織り込まれて物価の下落率が大きくなることは、本件改定が始まった平成25年には明らかであった。したがって、本件改定は、違法であり少なくとも過失も認められると考えられる。
次に、上告人らに慰謝すべき精神的損害が生じているかを検討することとする。生活保護法8条2項は、「最低限度の生活の需要を満たすに十分なもの」となるように保護基準を定めることを厚生労働大臣に義務付けており、本件改定が、違法に引下げ幅を拡大して、その結果、上告人らが「最低限度の生活の需要を満たす」ことができない状態を9年以上にわたり強いられてきたとすれば、財産的損害が賠償されれば足りるから精神的損害は慰謝する必要はないとはいえず、その額は、それぞれの請求額である1万円を下回らないと思われる。したがって、上告人Xの損害賠償請求は認容すべきと考える。
[1] この意味で令和7年6月27日日弁連会長声明中の「本判決は、厚生労働大臣が、「個人の尊厳」(憲法13条)の基盤となる「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(憲法25条1項、生活保護法3条)の重要性を軽視し、生活保護法8条2項によって考慮すべき事項を考慮せずに行った本引下げを違法として、これに基づく保護費減額処分の取消しを認めたものであり、司法が担う役割を十分に果たしたものと高く評価できる」とする部分は本判決を正しく理解していない。
[2] 同日日本司法書士会連合会会長声明は、「生活保護基準は、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の水準を具体化するものであるから、統計の数値や専門的知見に基づいて客観的に定められるべきである。また、生活保護基準の決定に際して考慮すべき事項は、生活保護法第8条第2項の趣旨に沿ったものでなければならず、これ以外の事項が考慮されることはあってはならないし、それらの事項の採否、具体的な適用の在り方及びそれらの検討過程に係る国民への周知についても、生活保護制度の趣旨に沿った合理的なものが求められる。この点、本判決は、統計等、政策判断における専門技術的な考察において取り扱われるものの在り方につき、それらのものと政策判断との間の合理的関係性や専門的知見との整合性のみならず、専門的知見に基づく説明その他の周知が十分に行われることの重要性も大枠として示しており、今後の我が国における政策決定の在り方につき、多くの示唆を含む」と本判決を正解しているように思われる。